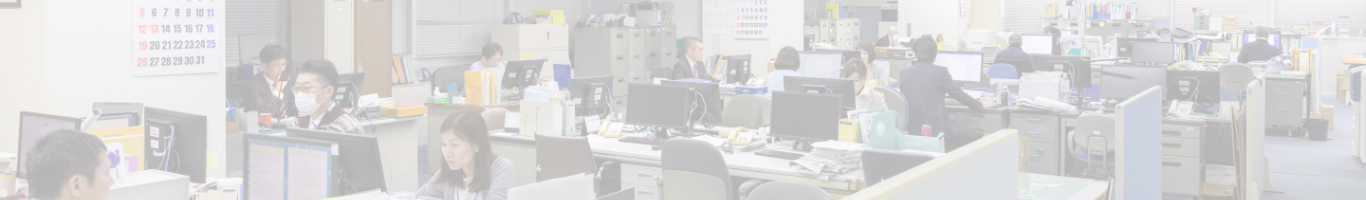
事業承継
カテゴリ・年で絞り込む
事業承継
-
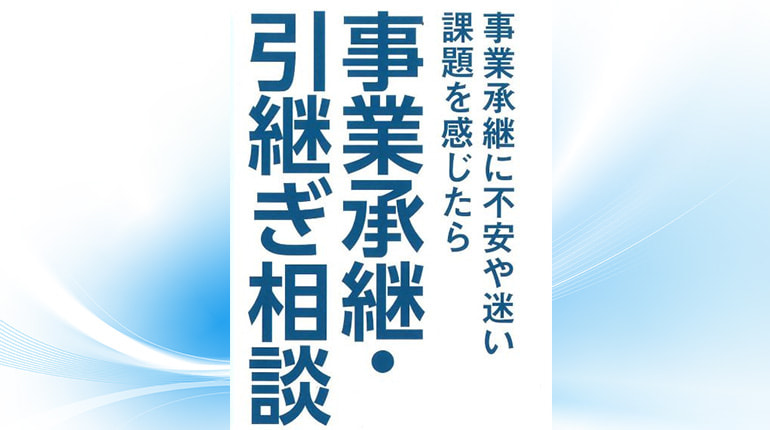 掲載日:2024年02月13日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します2(第3回 相続税の非課税財産) 「贈与」とは、民法上、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。
掲載日:2024年02月13日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します2(第3回 相続税の非課税財産) 「贈与」とは、民法上、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。 -
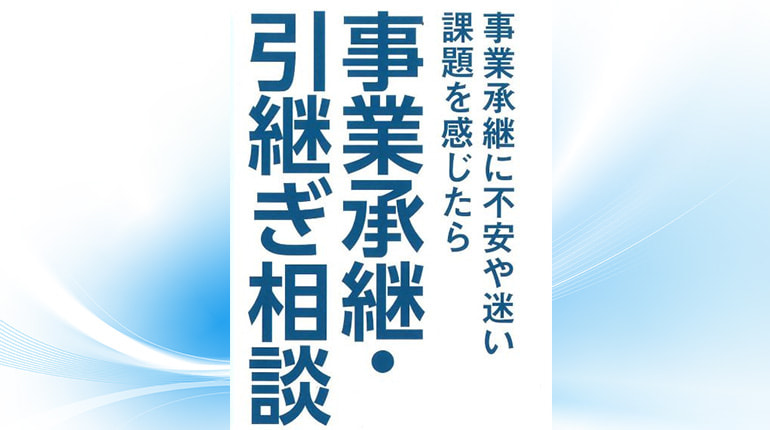 掲載日:2024年02月05日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します2(第2回 相続税の課税財産) 相続の開始があった場合には、相続人は、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。一般には、被相続人に帰属していた財産上の権利義務のうち、相続又は遺贈により相続人又は受遺者が取得するものが本来の相続財産であり、相続税法では、被相続人に帰属していた財産のうち、金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全ての積極財産が課税の対象となります。
掲載日:2024年02月05日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します2(第2回 相続税の課税財産) 相続の開始があった場合には、相続人は、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。一般には、被相続人に帰属していた財産上の権利義務のうち、相続又は遺贈により相続人又は受遺者が取得するものが本来の相続財産であり、相続税法では、被相続人に帰属していた財産のうち、金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全ての積極財産が課税の対象となります。 -
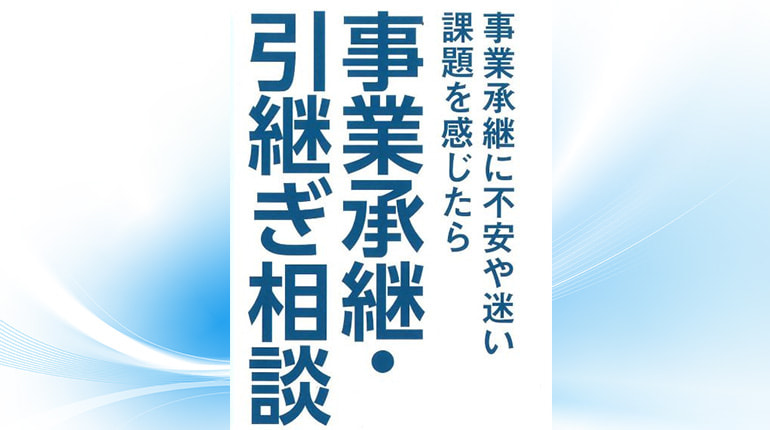 掲載日:2024年01月29日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します2(第1回 相続) 相続人の範囲と順位および法定相続分とは、どのようなものか。
掲載日:2024年01月29日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します2(第1回 相続) 相続人の範囲と順位および法定相続分とは、どのようなものか。 -
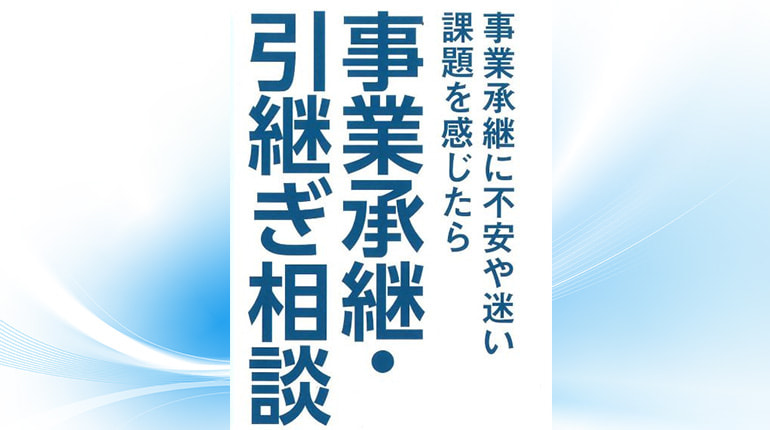 掲載日:2024年01月22日 株主構成を確認しよう!同族会社のリスクと対策 ご本人以外に会社の経営に関係のないご親戚やご友人、創業当時の従業員などのお名前はありませんか。
掲載日:2024年01月22日 株主構成を確認しよう!同族会社のリスクと対策 ご本人以外に会社の経営に関係のないご親戚やご友人、創業当時の従業員などのお名前はありませんか。 -
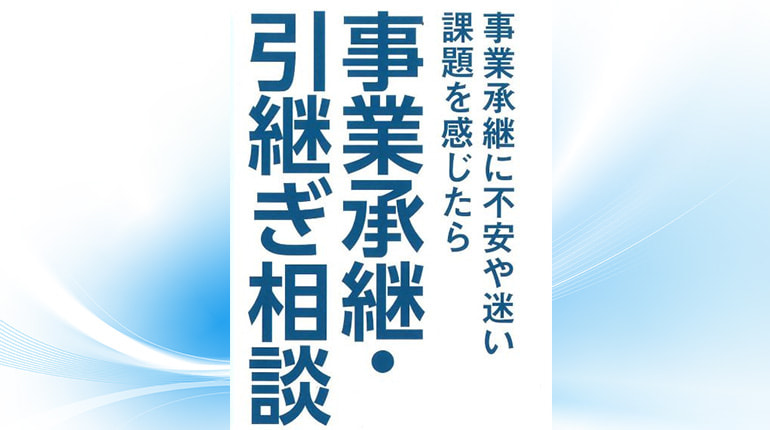 掲載日:2024年01月15日 後継者問題を解決するための種類株式の活用法 会社法では、株主の多様なニーズに配慮して、会社が一定の事項について、内容の異なる2以上の種類の株式(種類株式)を発行することを認めています。 種類株式を活用することによって、後継者に議決権を集中させることや先代経営者が後継者に事業を継がせた後も、後継者者をけん制し、あるいはその暴走を阻止する仕組みづくりが可能です。
掲載日:2024年01月15日 後継者問題を解決するための種類株式の活用法 会社法では、株主の多様なニーズに配慮して、会社が一定の事項について、内容の異なる2以上の種類の株式(種類株式)を発行することを認めています。 種類株式を活用することによって、後継者に議決権を集中させることや先代経営者が後継者に事業を継がせた後も、後継者者をけん制し、あるいはその暴走を阻止する仕組みづくりが可能です。 -
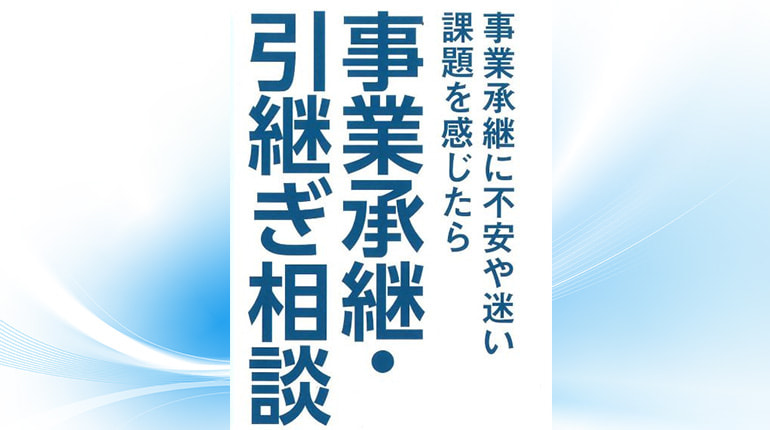 掲載日:2024年01月09日 金庫株制度の活用で後継者問題を解決! 「金庫株」とは、会社が発行済の自社株を株主から買い戻し、消却や譲渡をせずに金庫に保管するなどして手元に置き、自社で保有する自社株式のことをいい、正式には「自己株式」といいます。
掲載日:2024年01月09日 金庫株制度の活用で後継者問題を解決! 「金庫株」とは、会社が発行済の自社株を株主から買い戻し、消却や譲渡をせずに金庫に保管するなどして手元に置き、自社で保有する自社株式のことをいい、正式には「自己株式」といいます。 -
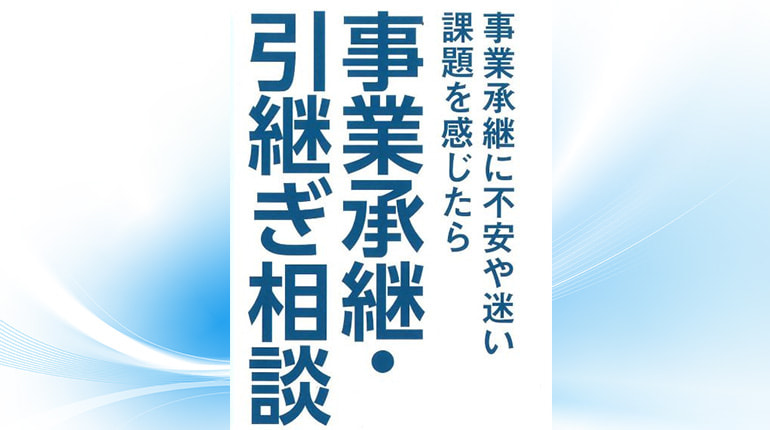 掲載日:2023年12月25日 遺留分に関する民法の特例について解説します 相続人は、原則として被相続人の財産を引継ぎますが、その財産に多額の債務があり相続したくない場合もあります。このような場合は相続を放棄するか、あるいは承認する場合でも積極財産の範囲内で消極財産を受け継ぐことが認められています。
掲載日:2023年12月25日 遺留分に関する民法の特例について解説します 相続人は、原則として被相続人の財産を引継ぎますが、その財産に多額の債務があり相続したくない場合もあります。このような場合は相続を放棄するか、あるいは承認する場合でも積極財産の範囲内で消極財産を受け継ぐことが認められています。 -
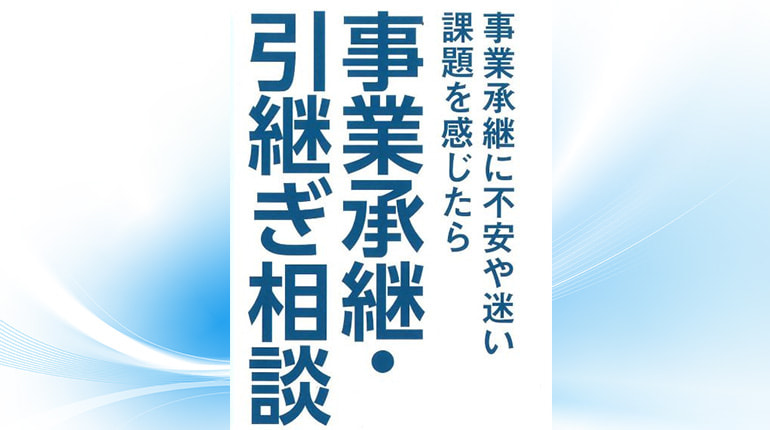 掲載日:2023年12月18日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します(最終回 贈与税の申告と納税 ) 贈与税の申告書の提出期限は、贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日です。
掲載日:2023年12月18日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します(最終回 贈与税の申告と納税 ) 贈与税の申告書の提出期限は、贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日です。 -
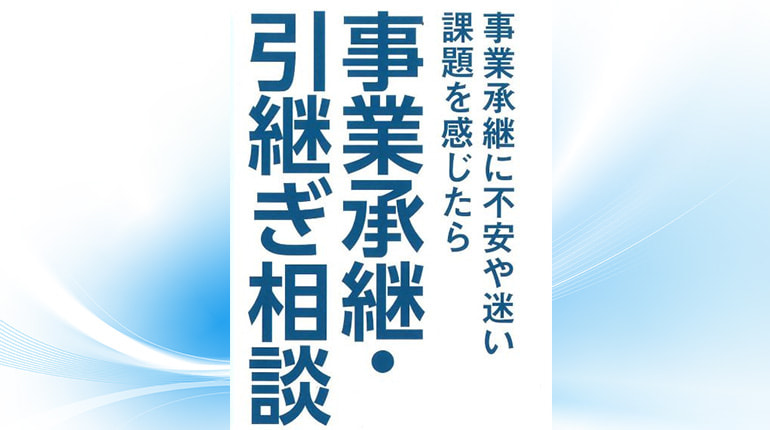 掲載日:2023年12月11日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します(第4回 相続時精算課税制度 ) 相続時精算課税制度は、高齢化の進展に伴い、相続による次世代への資産移転の時期が従来よりも大幅に遅れてきていること、高齢者の保有する資産の有効活用を通じて経済社会の活性化にも資するといった社会的要請を踏まえ、生前における贈与による資産移転の円滑化に資することを目的として、平成15年度税制改正において創設されたものです。
掲載日:2023年12月11日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します(第4回 相続時精算課税制度 ) 相続時精算課税制度は、高齢化の進展に伴い、相続による次世代への資産移転の時期が従来よりも大幅に遅れてきていること、高齢者の保有する資産の有効活用を通じて経済社会の活性化にも資するといった社会的要請を踏まえ、生前における贈与による資産移転の円滑化に資することを目的として、平成15年度税制改正において創設されたものです。 -
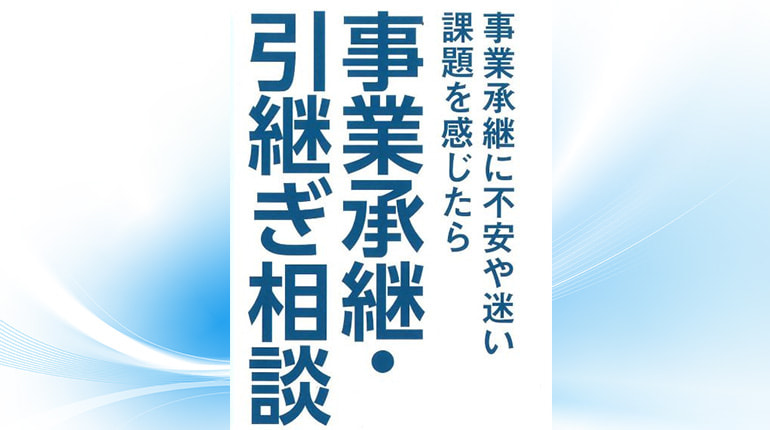 掲載日:2023年12月04日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します(第3回 贈与税の課税価格と税額の計算 ) 贈与税の課税価格は、その年1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産及び贈与により取得したものとみなされる財産の価額の合計額です。 贈与税の税額の計算は、課税価格から、贈与税の「基礎控除」及び「配偶者控除」を控除した後の金額に税率を適用して、納付すべき税額を計算します。
掲載日:2023年12月04日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します(第3回 贈与税の課税価格と税額の計算 ) 贈与税の課税価格は、その年1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産及び贈与により取得したものとみなされる財産の価額の合計額です。 贈与税の税額の計算は、課税価格から、贈与税の「基礎控除」及び「配偶者控除」を控除した後の金額に税率を適用して、納付すべき税額を計算します。 -
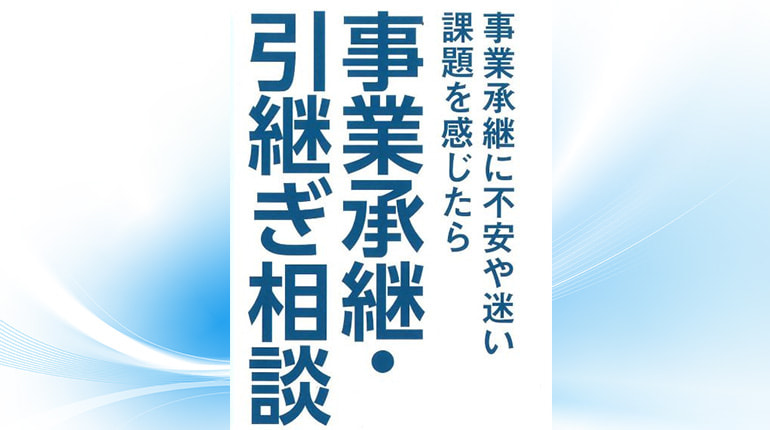 掲載日:2023年11月27日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します(第2回 贈与税の課税財産 ) 「贈与」とは、民法上、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。
掲載日:2023年11月27日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します(第2回 贈与税の課税財産 ) 「贈与」とは、民法上、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。 -
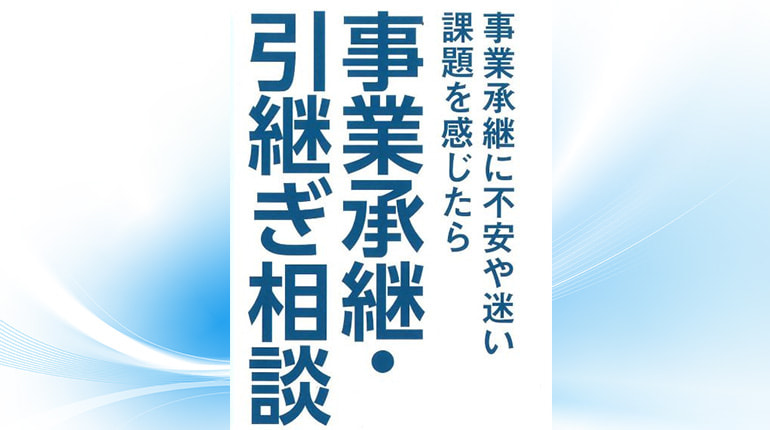 掲載日:2023年11月20日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します(第1回 贈与 ) 「贈与」とは、民法上、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。
掲載日:2023年11月20日 事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します(第1回 贈与 ) 「贈与」とは、民法上、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。