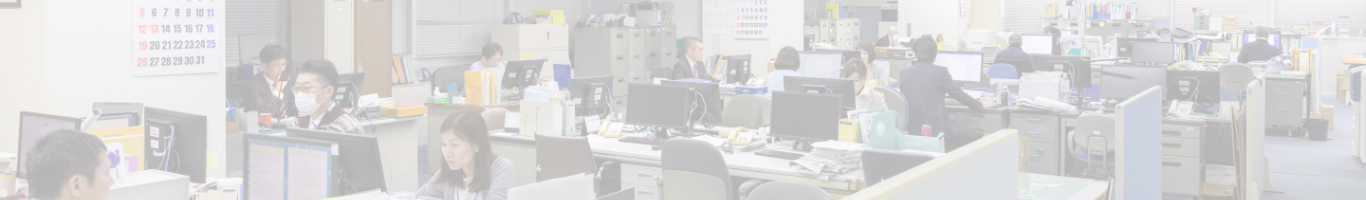経営総合相談窓口の現場から~「購入強制・不当な給付内容の変更・支払遅延」
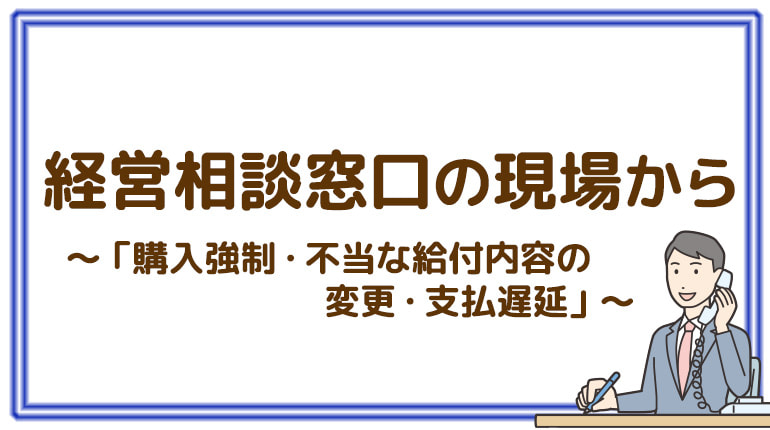
経営総合相談窓口の現場から
今回は、「購入強制・不当な給付内容の変更・支払遅延」の事例について掲載いたします。
相談事例:「購入強制・不当な給付内容の変更・支払遅延」
A社は、資本金500万円の中小企業です。発注先のB社(資本金5億円)から機械部品の製造委託を請負っています。A社はB社から加工機械をリースしていましたが、買い取りを求められやむなく買い取りました。また、B社からの発注は電話等で連絡されますが、注文書に記載された納期と異なる場合が度々ありました。支払方法は毎月末日納品〆切翌月末日支払でしたが、実際には、翌々月末日に繰り延べられることもあり困っていました。こうした中、B社から「事業再編に伴い、A社との取引を終了する」旨の文書が突然送られてきました。
A社は今後どう対応したらいいか困り「下請かけこみ寺」に相談しました。
回答
A社とB社の取引は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の資本金基準(親事業者 資本金1,000万円超、下請事業者 資本金1,000万円以下又は個人事業者)を満たしており、「製造委託」に該当することから、下請法が適用される取引と考えられます。
B社の行為は、注文書に記載している納期と異なる納期を電話等により指示し、下請事業者に不利益に変更しており、下請法第4条第2項第4号「不当な給付内容の変更」、また、実際の納期を遅らせる場合には第4条第1項第1号「受領拒否」、これに伴う第4条第1項第2号「支払遅延」、実際の納期を前倒しして短くする場合には短納期発注による第4条第1項第5号「買いたたき」等のおそれがあると考えられます。
さらに、第4条第1項第6号の設備の「強制購入」のおそれもあります。
次に、「取引停止の通知」については継続的取引契約期間内であれば「事業再編のため」が中途解約事由に該当するのか、また、これがやむを得ない事由にあたるかなどを検討する必要があります。
A社には、以上のことを念頭にB社に交渉を申入れてはどうかとアドバイスをいたしました。