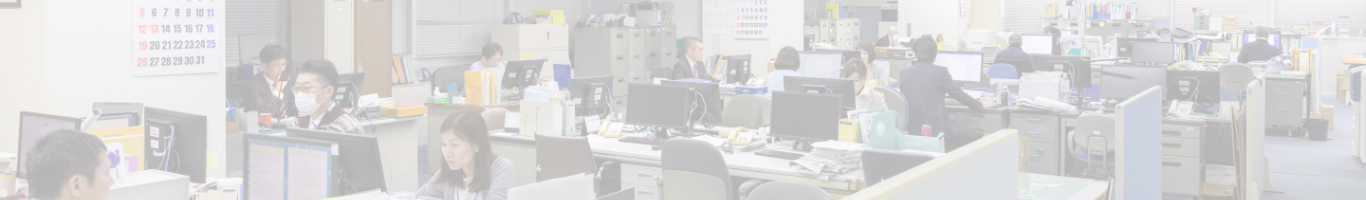事業承継に必要な税務の基礎知識について3(第1回 財産の評価 )
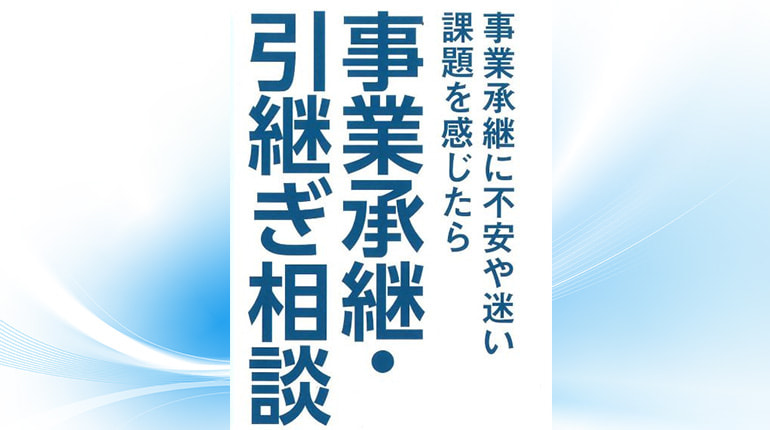
相続や贈与の理解には税務の知識が必要となりますが、特に自社株式の評価方法に関する重要なポイントのみに絞って6回シリーズで解説します。第1回は、「財産の評価」です。
財産の評価
相続税および贈与税の課税財産は、相続、遺贈又は贈与により無償で取得した財産であるため、その課税価格の計算に当たっては、取得した財産をいくらに見積もるかという「財産の評価」が必要となります。
相続税法では、財産の評価に関しては、地上権、永小作権、定期金に関する権利等の財産についてその評価方法が規定されていますが、その他の財産の評価については、「時価」による旨だけが規定され、「時価」の内容は法律の解釈に委ねられています。
評価の原則
財産の評価については、その財産の取得価額による原価主義と、その課税時期における時価による時価主義の二つの方法がありますが、相続税法では、時価主義を基本原則としています。
なお、相続税法は、地上権、永小作権などの特定の財産以外の財産については、具体的な評価方法を定めていませんので、課税実務上は、「財産評価基本通達」に基づいて評価することとされています。
取引相場のない株式の評価方法
中小企業の皆さま方の事業承継で特に重要となるのが、オーナーさまが保有される自社株式の評価です。
しかし、中小企業の発行する株式(取引相場のない株式)には、金融商品取引所における市場取引や証券会社の店頭取引で成立するような取引価格というものがありません。
そこで、財産評価基本通達では、取引相場のない株式の価額を客観的・合理的に、かつ、その実態に即して評価することができるようにするため、その評価する株式の発行会社(評価会社)の規模に応じて、大会社、中会社、小会社に区分し、その規模区分に従いそれぞれの会社に適用すべき原則的な評価方式(原則的評価方式 ※1)を定めるとともに、その例外として、少数株主など会社支配権のない株主の取得した株式についての特例的な評価方式(特例的評価方式 ※2)を併せて定めています。
※1 原則的評価方式:同族間の相続や贈与に適用される評価方法
※2 特例的評価方法:少数株主に適用される評価方法
第2回は、「評価方法の判定」です。
「税務大学校 講本」(国税庁)を加工して作成
このブログ記事の詳細は、専門知識が必要となることも多いため、弁護士、税理士などの外部専門家へご確認されることをお勧めします。
ひとつでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください!
- 親族への計画的な事業引継をしたい!
- 従業員に後継者として会社を任せたい!
- 後継者候補を探してほしい!
- 他の企業に会社(事業)を売却したい!
- 他の企業(事業)を買収したい!
- 当事者同士では承継の合意はできているが不安!
神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターの特徴
神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターは、「産業競争力強化法」に基づき、公益財団法人神奈川産業振興センターが経済産業省関東経済産業局から委託を受けて実施している国の事業です。安心してご相談いただけます。
相談はすべて無料です。お気軽にご相談いただけます。
中小企業のM&A・事業承継に詳しい専門家が、秘密厳守でご相談を承ります。
| 神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター(外部専用サイト) |
相談のお申し込みは
相談予約申込書のダウンロード 事業承継・引継ぎ支援-相談予約申込書
インターネット相談予約 インターネット相談予約