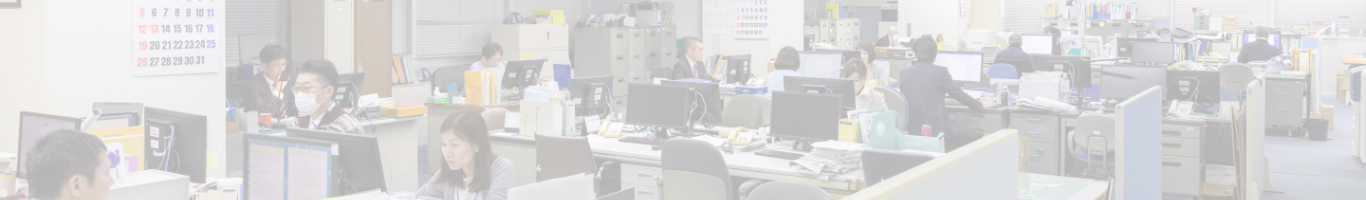事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します2(第4回 債務控除 )
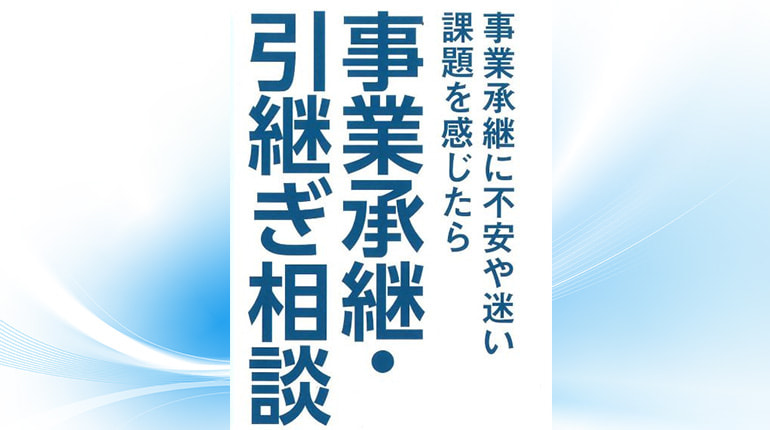
相続や贈与の理解には税務の知識が必要となりますが、特に相続税に関する重要なポイントのみに絞って7回シリーズで解説します。第4回は、「債務控除」について解説します。
債務
相続税法では、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。
また、葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
債務控除の対象となる債務とは
債務控除の対象となる債務は、次表のとおりです。
| (1) | 相続人または包括受遺者が承継した債務であること |
|---|---|
| (2) | 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(借入金、未払金および公租公課など。)であること |
| (3) | 確実と認められるものであること |
債務控除の対象とならない債務
被相続人の債務であっても、相続税の非課税財産である(1)墓所、霊びょうおよび祭具並びにこれらに準ずるもの、(2)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業の用に供する財産について、これらの取得、維持または管理のために生じた債務の金額は、その財産を課税価格に算入しないこととの見合いで、控除しないこととされています。
例えば、被相続人が生前に購入した墓碑の未払代金は、債務控除の対象とはなりません。
債務控除を適用できる者
債務控除を適用することができる者は、被相続人の相続人および包括受遺者です。
この「相続人」には、本来、相続を放棄した者または相続権を失った者は含まれませんが、これらの者であっても、被相続人の葬式費用を現実に負担した場合には、その負担額は債務控除をすることができることとして取り扱われています。
葬式費用
葬式費用は、相続税の課税価格の計算上、相続人または包括受遺者が負担したものを控除することとされています。
葬式費用は、前述の債務とは本質的に異なり、本来、遺族が負担すべきものであり控除できないようにみられますが、相続開始に伴う必然的出費であり、いわば相続財産そのものが担っている負担ともいえることを考慮して、控除することとされています。

債務控除の対象となる葬式費用とは
相続税法では明確な範囲を規定していませんが、次表のものが葬式費用として控除できます。
| (1) | 葬式若しくは葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納骨または遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用 |
|---|---|
| (2) | 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用 |
| (3) | (1)または(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの |
| (4) | 死体の捜索または死体若しくは遺骨の運搬に要した費用 |
葬式費用には該当しないもの
| (1) | 香典返れい費用 |
|---|---|
| (2) | 墓碑、墓地の購入費および墓地借入料 |
| (3) | 初七日、その他法要のための費用 |
| (4) | 医学上、裁判上など特別の処置に要した費 |
「税務大学校 講本」(国税庁)を加工して作成
次回は、相続税額の計算のしくみについて解説します。
このブログ記事の詳細は、専門知識が必要となることも多いため、弁護士、税理士などの外部専門家へご確認されることをお勧めします。
ひとつでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください!
- 親族への計画的な事業引継をしたい!
- 従業員に後継者として会社を任せたい!
- 後継者候補を探してほしい!
- 他の企業に会社(事業)を売却したい!
- 他の企業(事業)を買収したい!
- 当事者同士では承継の合意はできているが不安!
神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターの特徴
神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターは、「産業競争力強化法」に基づき、公益財団法人神奈川産業振興センターが経済産業省関東経済産業局から委託を受けて実施している国の事業です。安心してご相談いただけます。
相談はすべて無料です。お気軽にご相談いただけます。
中小企業のM&A・事業承継に詳しい専門家が、秘密厳守でご相談を承ります。
| 神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター(外部専用サイト) |
相談のお申し込みは
相談予約申込書のダウンロード 事業承継・引継ぎ支援-相談予約申込書
インターネット相談予約 インターネット相談予約