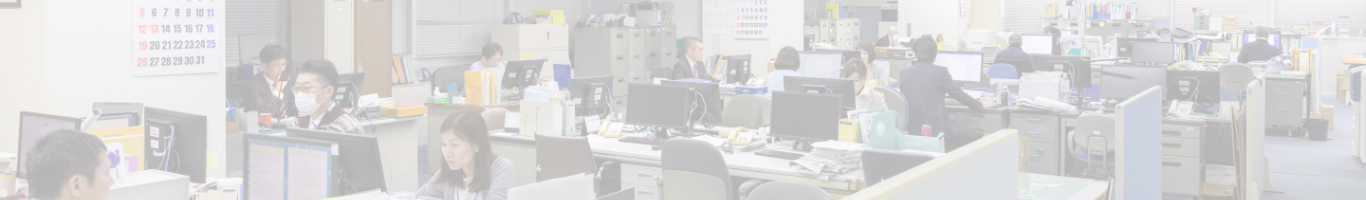設備投資
掲載日:2025年11月26日
中小企業の粉飾決算|与信審査における注意点

中小企業の粉飾決算|与信審査における注意点
本記事では、与信審査時に見る中小企業の粉飾決算の主な手口(資産・負債・純資産・収益・費用)を整理し、意図せざる粉飾を含め、なぜ粉飾が悪いのかを審査担当者視点で解説します。
与信審査では中小企業の財務状況を確認しますが、意図的でなくても数字が実態より良く見えてしまうケースがあります。そのため、粉飾決算は短期的に見栄えを良くしているように見える点に注意が必要です。
粉飾が悪である理由(要点)
- 外部ステークホルダー(金融機関、仕入先、投資家)が誤った判断をする:融資や取引継続の是非を誤らせる。
- 税務・法令リスク:発覚時には追加課税、罰金、場合によっては刑事責任に発展する。
- 内部管理の崩壊:実態把握ができなくなり、経営判断が誤る。
- 従業員や取引先への影響:雇用や支払いが不安定になり得る。
5勘定別:中小企業での典型的な粉飾事例(審査担当者視点)
| 勘定区分 | 粉飾の狙い | 具体的な手口(事例) |
|---|---|---|
| (1) 資産 | 財務体質の良化(自己資本比率向上など) |
|
| (2) 負債 | 負債比率を低く見せる |
|
| (3) 純資産 | 資本の健全性を偽装 |
|
| (4) 収益(売上) | 売上・利益を増やして好業績を装う |
|
| (5) 費用 | 費用を小さくして利益を水増し |
|
実務的な注意点(発覚しやすい場面)
- 金融機関の決算資料照会や追加資料要求時に齟齬が出ると発覚しやすい。
- 税務調査では、領収書・請求書類の整合性や取引先照会で不正が判明することが多い。
- 連結や第三者監査が入ると、帳簿の整合性が厳しくチェックされます。
まとめ なぜ粉飾は決して許されないのか
粉飾決算は短期的な便益(融資獲得や取引継続)をもたらすように見えますが、長期的には企業価値の毀損、法的制裁、社会的信用の喪失を招きます。 特に中小企業は人的・資本的余力が小さいため、発覚後のダメージが致命的になりやすい点に注意が必要です。 透明で正確な会計処理と内部統制の整備こそ、持続可能な経営の基礎です。
(本記事は一般的な会計解説です。実際の会計処理・開示判断は税理士・公認会計士等の専門家へご相談ください。)
参考文献・出典
- 中小企業庁『中小企業白書』(最新版)
- 金融庁『金融検査マニュアル別冊:中小企業融資編』
- 企業会計基準委員会(ASBJ)『中小企業の会計に関する指針』(令和7年9月19日修正版)
- 都井清史『コツさえわかればすぐ使える粉飾決算の見分け方』